細田守監督の映画『バケモノの子』には、熊徹や猪王山など個性的なバケモノたちが登場します。
彼らの姿や性格は、西洋のモンスターというよりも、どこか日本の民話や妖怪の面影を感じさせます。
本記事では、登場キャラクターの造形や世界観を通じて、「日本的な妖怪文化」とのつながりを考察していきます。
熊徹のモデルは「鬼」や「熊の妖怪」?
主人公・九太の師匠となる熊徹(くまてつ)は、その名の通り熊のような姿をした豪快な戦士です。
性格は荒っぽい一方で情に厚く、人間臭い不器用さを持っています。
この熊徹のモデルとして考えられるのが日本の「鬼」や「熊の精霊」です。
鬼は力と怒りを象徴する存在でありながら、古来より人間と深く関わってきた妖怪の一種です。
熊徹もまた、暴力的な力を持ちながらも「強く生きる意味」を求め、弟子を導こうとする姿が描かれています。
その姿には、鬼が持つ「恐れられつつも人を映す鏡」という性質が重なります。
猪王山は「山の神」の象徴
熊徹のライバルである猪王山(いおうざん)は、穏やかで理知的な性格を持つ猪のバケモノです。
彼の名は「山」を冠しており、古来から信仰されてきた山の神や猪神を想起させます。
日本の山岳信仰では、猪は作物や自然の守護者として崇められてきました。
猪王山が息子の一郎彦を厳しく育てる姿は、自然界の厳しさと同時に、親としての深い慈しみも感じさせます。
つまり彼は、単なる敵役ではなく「自然の秩序」を体現する存在なのです。
渋天街という異界と妖怪的世界観
『バケモノの子』の舞台となる渋天街(じゅうてんがい)は、現実と異界のあいだに存在する幻想都市です。
この「人間界と交わらない世界」は、民話や妖怪伝承における「隠世(かくりよ)」の概念に近いものです。
妖怪は人間の想像力の中で生まれ、社会の裏側に潜む存在として描かれてきました。
細田監督はこの世界を通して、「人間ではない存在たちが持つ社会」を描きながら、
実は私たちの社会の縮図を投影しています。
つまり、渋天街は現実の人間社会を別の形で映した【もうひとつの日本】なのです。
細田守監督が描く異形の意味
細田監督作品では、異形の存在がしばしば登場します。
『おおかみこどもの雨と雪』では「人間とおおかみの間」、本作では「人間とバケモノの間」。
どちらも、境界に生きる者たちを通して、人間の多様な生き方を描いています。
熊徹たちは人間ではありませんが、その悩みや葛藤は人間そのもの。
細田監督は妖怪を「恐れる存在」ではなく、「人間を映す鏡」として描いています。
これこそが、西洋のモンスター映画とは異なる、日本的なバケモノの魅力です。
まとめ:妖怪は「人間の心を映す鏡」
『バケモノの子』の登場人物たちは、古来の妖怪がそうであったように、人間の心の姿を象徴する存在です。
熊徹は怒りと情、猪王山は理性と自然の力――。
それぞれが人間の内にある相反する感情を具現化しています。
細田守監督は、妖怪というフィクションを通して、「人間とは何か」を問うています。
だからこそ『バケモノの子』は単なる冒険物語ではなく、現代の人間の心を映した神話なのです。
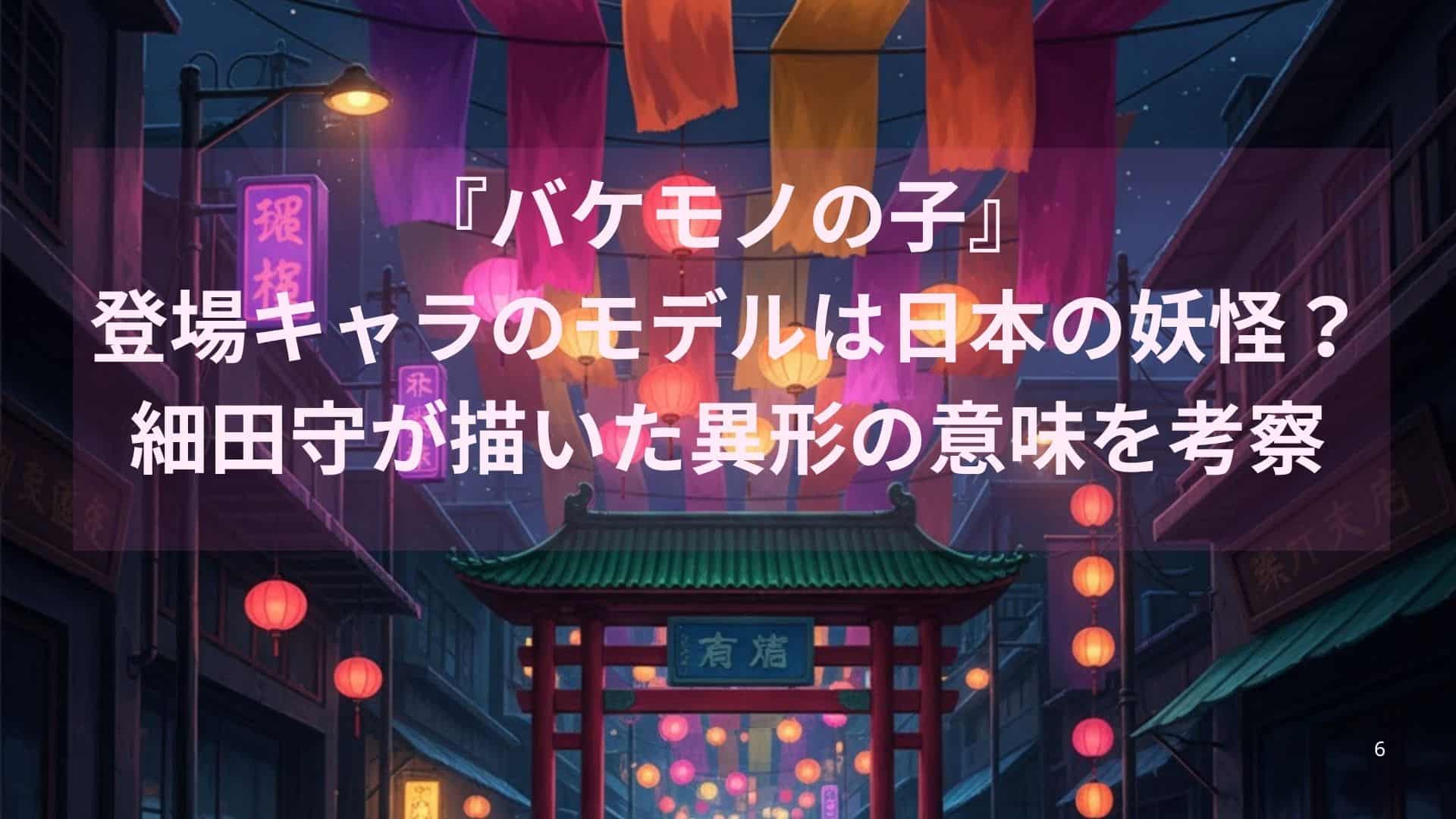


コメント