スタジオジブリ作品『火垂るの墓』は、戦争が子どもたちに何をもたらしたかを描いた不朽の名作です。多くの人が涙を流したであろう、節子の死ですが、その後に待っていた清太の運命もまた、戦争の残酷さを物語っています。
清太の死は終戦「後」だった
『火垂るの墓』の冒頭で、清太が駅構内で息絶えるシーンがあります。このときのナレーションで、「昭和二十年九月二十一日、僕は死んだ」と語られます。これは、終戦の詔書が出された「8月15日」から一か月以上経った頃のこと。つまり、清太は終戦を生き延びたにもかかわらず、その後に命を落としているのです。
終戦後の混乱と無関心
戦争が終わったからといって、すべてが元に戻るわけではありませんでした。都市部では焼け野原の中、食料は不足し、孤児が路上で飢えに苦しんでいました。
清太が命を落とした神戸駅構内では、実際に多くの孤児が死亡していたとされています。
人々が日々の生活に精一杯で、他者に手を差し伸べる余裕がなかったのです。
清太が持っていたもの
清太の遺体のそばには、空になったドロップの缶がありました。中には、節子の遺骨が入っていたと言われています。妹の亡き後も、その存在を手放せなかった清太。最後の最後まで「兄」であろうとした彼の姿が、胸を締めつけます。
駅員がドロップ缶を外に投げ捨てるシーンも他者、子どもの亡骸に対して無関心で日常の出来事だったことが伝わるシーンでした。
もう少しで救われた命だったのか?
もし清太が、もう少し大人に助けを求められていたら。もし、誰かが清太たち兄妹に手を差し伸べていたら…。 終戦直後という、社会全体が疲弊しきった中でも「あと少し」の差で助けられた命だったかもしれません。
作品が語る終戦の意味
『火垂るの墓』は、ただの戦争映画ではありません。戦争が終わっても救われない命があること、そして「終戦=平和」ではないという現実を私たちに突きつけます。
清太の死は「戦争の終わり」による希望ではなく「戦争が遺した悲劇の継続」であり、その象徴と言えるのではないでしょうか。
まとめ
『火垂るの墓』で清太が亡くなったのは、終戦後の9月21日。節子の死後、たった一人で生き抜こうとした末の悲しい最期でした。
戦争が終わっても、すぐにすべてが元に戻るわけではない。清太の最期は戦争の残酷さと「その後」の現実を静かに力強く訴えかけてきます。
あちらの世界で節子やご両親と再会出来たでしょうか。清太の魂が安らかであることを心から祈ります。そして同じように辛く悲しい思いをしてきた数多くの子どもたち。
二度とこのような悲しい出来事が世界からなくなることを願ってやみません。
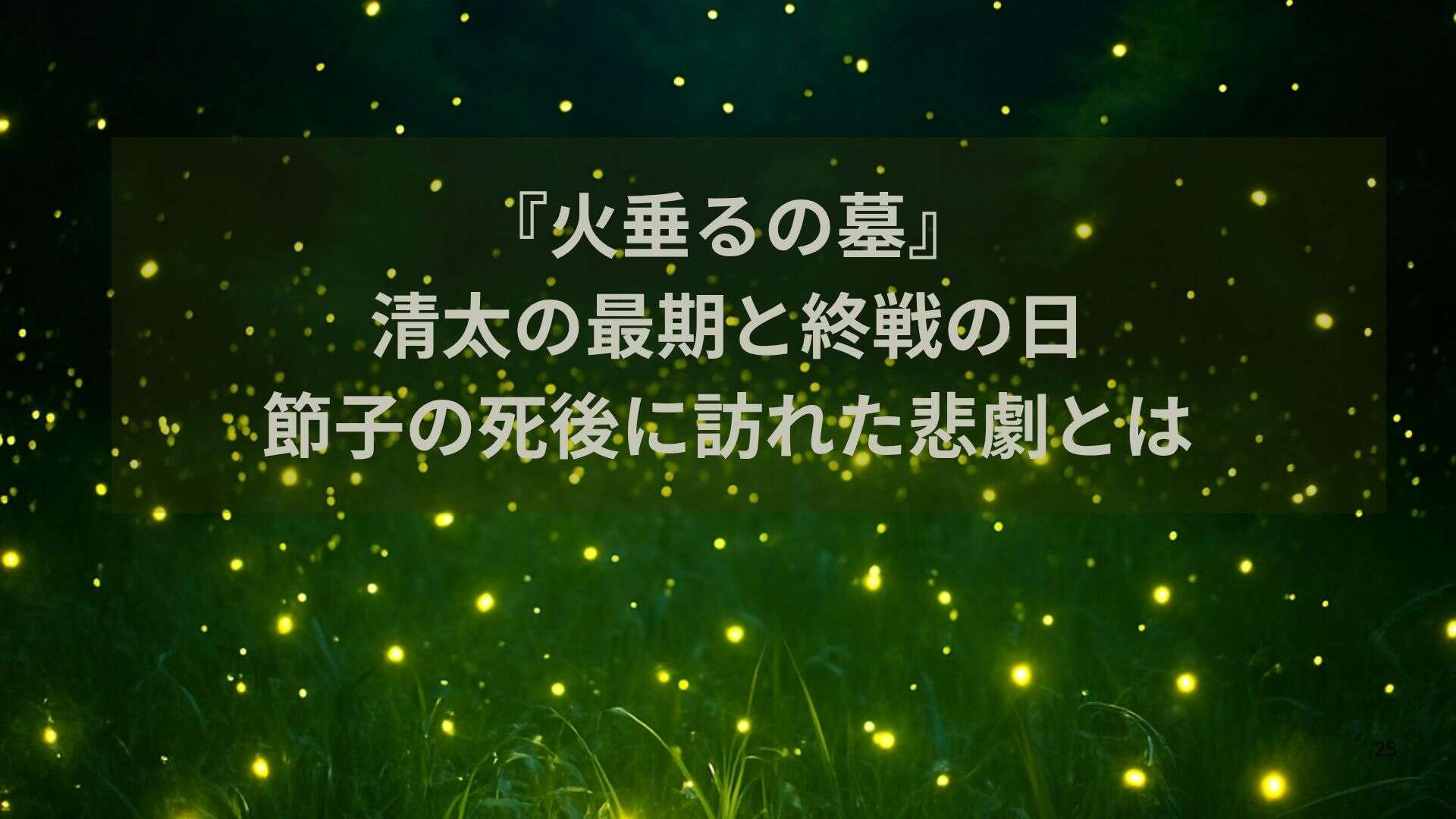


コメント