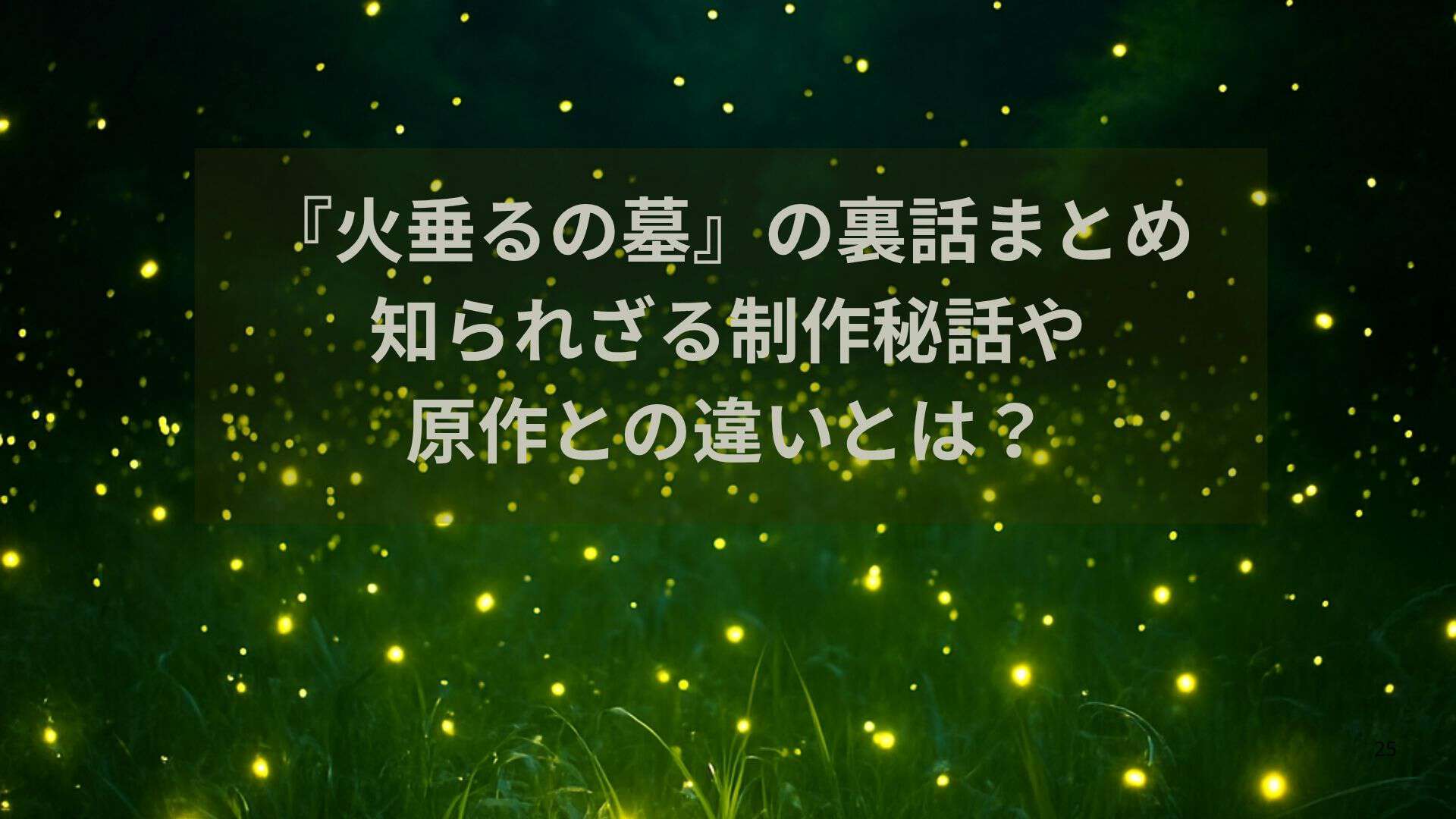スタジオジブリの代表作のひとつ『火垂るの墓』。涙なくしては見られないその内容には、実は多くの知られざる裏話や制作秘話が存在します。
今回は、火垂るの墓 裏話」や「制作エピソード」「原作との違い」などの観点から、作品の背景に迫ります。
原作は作者・野坂昭如の実体験
『火垂るの墓』の原作は、作家・野坂昭如による同名小説。これは彼自身の実体験に基づいて書かれた半自伝的小説です。
野坂氏は実際に妹を戦時中に亡くしており、その罪悪感と後悔を込めてこの作品を書いたと語っています。
小説の清太はアニメよりも自己中心的に描かれており、作者自身の“悔恨の念”が色濃く反映されています。
高畑勲監督・異例の単独作品
ジブリ作品として有名な本作ですが、実は当初からジブリ制作ではなく、同時上映だった『となりのトトロ』とセットで作られた背景があります。
高畑勲監督は戦争体験のない世代にも“感情を通して戦争を伝える”ことを目的とし、派手な演出を排したリアリズム重視の作風で制作しました。
実写に近い背景描写や、無音の間(ま)の使い方などは、その哲学の表れです。
あえて声優ではない俳優を起用
清太の声を務めたのは当時14歳の辰巳努さん。プロの声優ではなく、素朴な少年らしさを表現するために選ばれました。
一方、節子の声を演じた白石綾乃さんも実際に4歳。セリフのほとんどはアドリブや自然な話し方で録音されており、そのリアリティが作品全体の雰囲気を高めています。
映画と原作の違い
原作の清太は、アニメ版に比べてもっと自分勝手で反抗的な一面を持っています。
高畑監督は「読者が嫌悪感を持つような主人公を描くのは映画では難しい」とし、アニメ版ではより共感しやすい清太像を目指しました。
また、映画では節子視点の描写が多く、兄妹愛がより前面に出る構成になっています。
ラストシーンの神戸の夜景は実在の風景
ラストで清太と節子が見下ろす神戸の夜景は、実際の摩耶山からの景色がモデルとなっています。
現代の平和な日本と、焼け野原だった時代の記憶を重ねる象徴的な演出として高く評価されています。
まとめ:『火垂るの墓』に込められた裏の真実
『火垂るの墓』は、ただの戦争アニメではなく、原作者の実体験、高畑監督の演出哲学、声優選び、原作との違いなど、無数の“想い”が込められた作品です。
これらの裏話を知ることで、作品への理解がより深まり、また違った視点で涙することになるかもしれません。