細田守監督の『バケモノの子』は、少年・九太(蓮)が孤独の中で生き方を見つけていく物語です。
彼が「バケモノの子」と呼ばれる理由には、両親の不在が深く関わっています。
映画では父と母の存在がほんのわずかに描かれるだけですが、その描かれなさこそが、作品全体のメッセージを支える重要な要素なのです。
九太の幼少期と母の死
物語の冒頭、九太は母親と二人暮らしをしていました。父親とは離れて暮らしており、母が唯一の家族でした。
しかし、その母親が突然の交通事故で亡くなってしまいます。九太にとってこの出来事は、世界のすべてを失う瞬間でした。
家も、家族も、居場所もなくなった少年は渋谷の街をさまよい、やがてバケモノの世界「渋天街」へと迷い込みます。
細田監督はこのシーンで、少年が「生まれ変わる物語」の始まりを象徴的に描いています。
親という支えを失うことが、彼の新たな成長の出発点だったのです。
父親との距離と再会
九太の父親は、母親と別居していたことが示唆されています。
映画の後半で彼は再び登場しますが、九太はその存在を拒絶しようとします。
長い間離れていた父親に対して、九太は「今さら何を言えるのか」という反発心を抱いていました。
しかし、熊徹との生活を通じて学んだ「他者と向き合う強さ」が、九太を変えていきます。
父との再会は、彼が渋天街から現実へ戻るための試練でもありました。
それは、過去を受け入れる勇気を試す瞬間だったのです。
両親の不在は物語の装置ではなくテーマの中核
『バケモノの子』で両親が詳細に描かれないのは、意図的な演出だと考えられます。
細田守監督は、これまでの作品(『時をかける少女』『サマーウォーズ』『おおかみこどもの雨と雪』など)でも「家族」を中心テーマにしています。
しかし本作では血のつながりではない家族を描くことに重点を置きました。
そのため、九太の実の両親はあくまで「出発点」であり、
物語が本当に描きたかったのは、熊徹との絆や、渋天街という『もう一つの家庭』なのです。
熊徹が「もう一人の父」として描かれた理由
熊徹は粗野で乱暴ですが、どこか不器用に九太を育てようとします。
この関係は、実の父子ではなくとも本当の親子のような温かさを感じさせます。
熊徹が「心の強さ」を教えたことで、九太は血のつながりではない生きる絆を知りました。
九太の両親が不在であることにより、熊徹という存在の意味がより強調されています。
それは、血よりも心で結ばれる家族の形。
細田守監督が描き続けてきた“新しい家族像”の集大成と言えるでしょう。
両親の影が九太に与えた生きる動機
母を失い、父から離れたことで、九太は孤独と憎しみの中で成長しました。
しかし、彼が怒りのままに生きていた時期があったからこそ、熊徹との出会いに意味が生まれます。
もし両親が健在であれば、彼は渋天街に行くことも、熊徹に出会うこともなかったでしょう。
つまり両親の不在は、悲劇ではなく成長のための必然。
その喪失をどう受け止め、どう乗り越えるかが『バケモノの子』の核心なのです。
まとめ:親を失っても、人はつながりの中で生きていける
『バケモノの子』の九太にとって、両親の不在は「終わり」ではなく「始まり」でした。
彼は熊徹や楓、渋天街の仲間たちとの出会いを通じて、
親の愛を失っても、人は他者との絆の中で成長できるということを体現しました。
細田守監督は、九太の物語を通して家族とは血ではなく心でつながるものというメッセージを描いています。
九太の両親が静かに物語の背後にいることで、
そのテーマはより普遍的で、深い余韻を残すものとなっているのです。
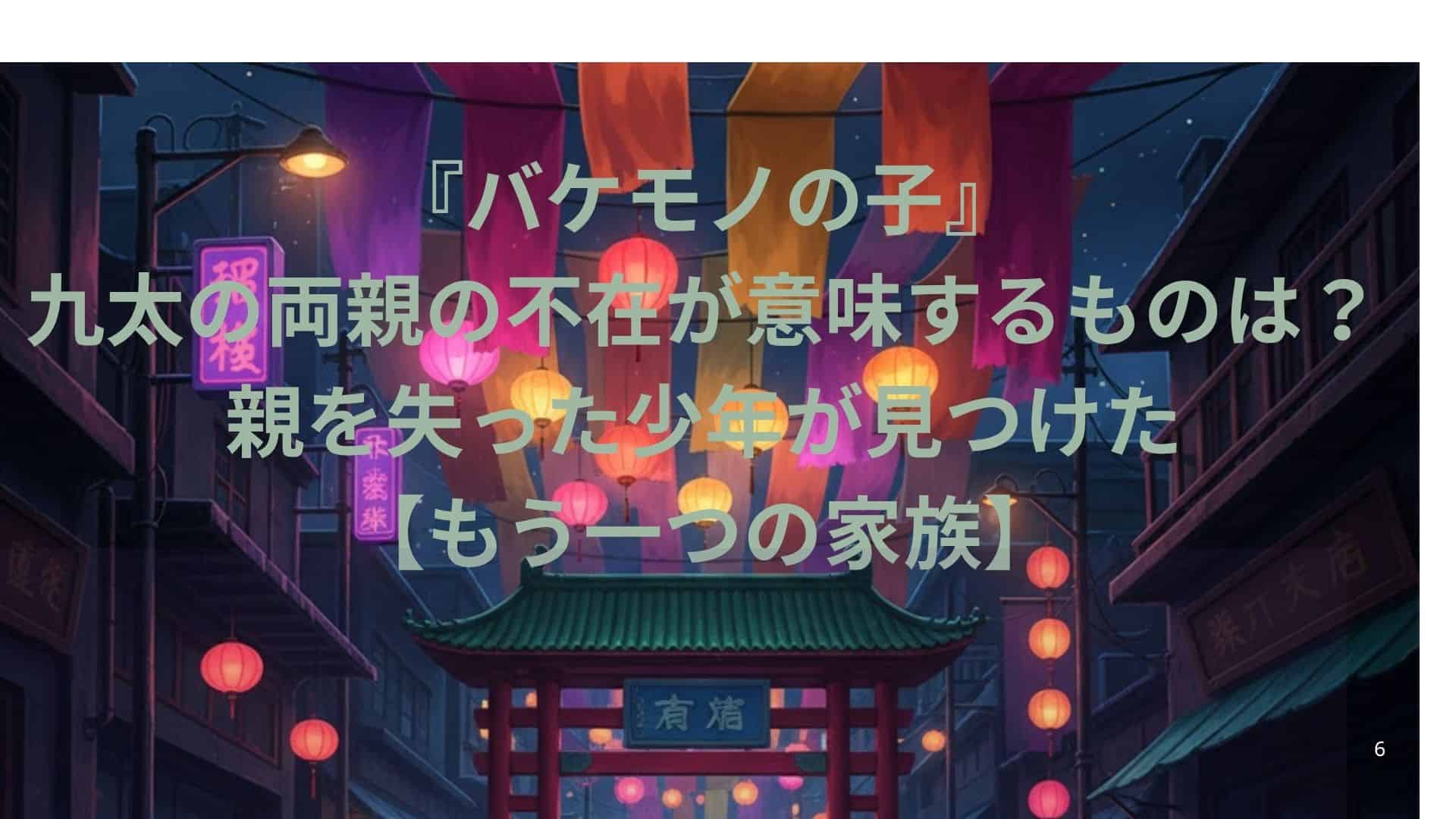


コメント